③各論・M&A豆知識 税理士事務所の合併・承継セミナー
- 大竹 邦明

- 2025年3月17日
- 読了時間: 5分
更新日:2025年7月28日
後継者不在・職員の雇用継続・顧問先へのサービス継続に悩む所長が多い「税理士事務所のM&A」。全国から承継・合併・税理士法人化の相談が寄せられる株式会社KACHIELの税理士専門のM&Aコンサルタント大竹邦明氏によるセミナーをお届けします。ネット検索すればすぐに調べられる表層の知識ではなく、現場目線のリアルな経験談をお話ししました。
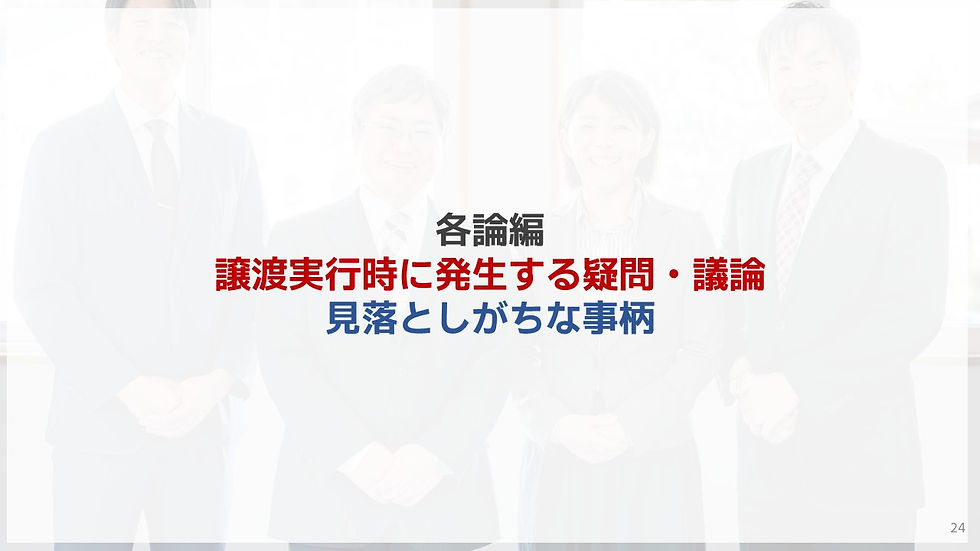
大竹:はい、それでは実行していく中で、各論的なおまけの情報にはなってくるんですけども、事業譲渡時に発生する疑問や論点、見落としがちな事柄について、いくつかご紹介させていただきます。
譲渡後のポジション・役割
まず、譲渡後の所長(譲渡側)のポジションと役割についてですが、どのようなケースが多いかというと、個人事務所が税理士法人の支店になり、元の所長が現役続行する場合、拠点の継続を希望されることが非常に多いですね。そのため、スタート時点では社員税理士になっていただくことが一般的かなと思います。
譲受側(買い手)の事務所からは、最初は「所属税理士になってほしい」という希望をいただくケースも多いのですが、実際には最初から適切な税理士資格者を新たな支店に配置するのが難しいため、信頼できる先生であれば社員税理士で問題ないと判断されるケースが非常に多いですね。
社員税理士となる場合の出資額
次に、出資額についてですが、税理士法人の出資額は比較的少額であることが多く、過去には現物出資が行われるケースもありました。
社員税理士となる場合の役員報酬
役員報酬の設定については、譲渡後の継続期間は、個人事務所時代や譲渡前の所得をベースに、おおよそ70%から80%の範囲で設定されることが多いですね。さらに、引き継ぎが進むにつれてご自身の役割も減少していくため、それに応じて役員報酬自体も減額していくのが一般的な流れになります。

会計ソフト
会計ソフトについては、譲渡後も同じソフトを利用し続けるケースがほとんどです。ほぼすべての事務所で、既存のシステムをそのまま使い続ける形になります。ただし、職員の理解が得られれば、業務効率化の観点からソフトを変更するケースも一部にはあります。
職員の雇用継続・待遇
就業規則や個別の労働条件に関しては、譲渡後1年ほどは現状維持とし、拠点別のルールをそのまま継続するケースが多いように思います。また、個別の雇用契約に関しても、基本的には現状維持で引き継ぐことが一般的ですが、契約書自体は譲渡先の事務所のフォーマットに落とし込む形で調整することが多く、ここに時間をかけて対応する必要が出てきます。

次に、退職金制度についてですが、個人事務所では職員に対して中退共などで積み立てを行っているケースが多いです。譲渡時には、譲渡先の事務所の制度に統一されるのが一般的ですが、譲渡先に退職金制度がない場合は、譲渡時に職員に対して一度退職金支給するケースがあります。
また、職員の不安を解消するために、これまでの退職金制度の掛金相当額を給与に上乗せし、新たな雇用条件として設定するケースも一部にはあります。
譲渡先でも同じ退職金制度が導入されている場合には、名義変更のみで継続可能なケースが多いですが、担当者によっては「一度解約が必要」と説明されることもあるようです。

顧問先との契約・顧問料徴収方法
次に、顧問契約や顧問料の徴収方法についてです。顧問契約書や収納代行サービス(口座振替など)については、譲渡後すぐに統一するケースが多いですね。ただし、新たに収納代行サービスを導入する場合、口座開設から引き落とし開始まで約3か月かかることが一般的なので、その間は個別に精算が必要になる点を把握しておくことが重要です。
また、事業譲渡時には収納代行サービス引継ぎを名義変更で対応できることも多く、利用するサービスが同じであれば基本的には引き継ぎが可能です。

税賠保険
税賠保険についても見落としがちですが、譲渡側の事務所で加入していて、譲渡先の事務所が未加入の場合でも、過去の保険契約を活用できるケースがあります。補償期間延長の特則を申請すれば、新たな掛金を支払うことなく過去分の補償を10年間延長できるため、これはぜひ押さえておきたいポイントです。
所長個人の車両
次に、所長個人の車両についてです。個人で長年使用していた車両のノンフリート等級の引き継ぎが可能かという点ですが、保険会社によっては特認申請での対応が可能なケースもあるようです。ただし、手続きが複雑で時間がかかるため、譲渡後は経費精算や手当てで対応するケースが多いようです。
過去に支給を受けたIT導入補助金
最後に、IT導入補助金についてです。会計ソフトの更新などでIT導入補助金の支給を受けている場合、事業譲渡に伴い返金が必要になるのではないか、という不安を持たれる方も多いです。実際にソフトベンダーの担当者に質問してみると「譲渡すると補助金の返金が必要」と言われることがあるようですが、IT導入補助金の事務局に問い合わせたところ、同じ事業が継続され、同じツールが引き続き使用される場合は、基本的に返金は不要との回答を得ています。この点については、直接事務局に確認するのが確実かと思います。
以上、今回は事業譲渡における各論的な内容についてお話ししました。次は、実際の実行者目線でどのような流れになるのかについて見ていきたいと思います。




コメント